|
|
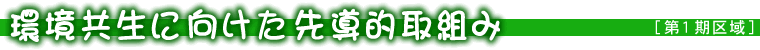
|
 |
「持続可能なコミュニティ形成に向けたまちづくり活動」
|
●目的 |
本事業で取り組んでいる「持続可能なコミュニティ」には、大きく2つの意味があると考えている。第1に、地球環境の「持続可能性」追求のための階層構造の1つとしての位置づけである。すなわち、国際レベル、国レベル、地方自治体レベル、コミュニティレベル、世帯レベルというヒエラルキーの一層を担うものとしての役割である。第2の意味は、土地区画整理事業として街並みが形成されつつある北九州学術研究都市のまちづくりの一環という位置づけである。「持続可能性」追求は、地域住民が協働して取り組むことでまちづくりの機運を盛り上げる際の共通の目標としての位置づけとなる。
本事業では、その両方の目的をにらみながら、持続可能なコミュニティ形成のための指標とそれを用いたマネジメント手法の検討を目的とし、住民アンケート調査と住民ワークショップの実施・解析と、今後の運営方策について検討するものである。
|
|
●実施スケジュール |
|
アンケート |
| 調査対象 |
: |
ひびきの、塩屋、小敷の住民 |
| 調査時期 |
: |
発送 |
平成17年2月17日 |
| 締切 |
平成17年2月28日(町内会) |
| 平成17年3月4日(その他) |

アンケートの回収
| 対象 |
部数 |
回収数 |
回収率 |
| 地権者 |
160 |
32 |
20.0% |
| 町内会 |
30 |
26 |
86.7% |
| ひびきの東側・北側地区 |
80 |
25 |
31.3% |
| 教員宿舎 北九州市立大学 |
45 |
27 |
24.8% |
| 教員宿舎 早稲田大学等 |
64 |
| (居住地不明) |
- |
1 |
- |
| 計 |
379 |
111 |
29.3% |
|
 |
|
住民ワークショップ |
| 対 象 |
: |
ひびきの、塩屋、小敷の住民 |
| 開催日時 |
: |
平成17年10月22日 |
チラシの表紙
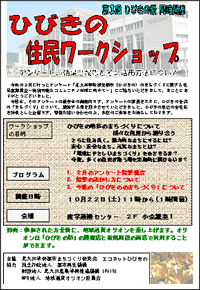
|
|
|
|
●研究の概要 |
まず、北九州学研都市の中に立地する宅地を対象としたコミュニティの持続可能性マネジメントに関して検討を行なった。そこではまず、コミュニティレベルでの評価指標について分析した。またGlobal Ecovillage Network (GEN)の開発した環境評価ツールであるCommunity Sustainability Assessment(CSA)を参考にしつつ、都市部に立地する新しいコミュニティを対象とした評価指標を検討した。これを踏まえ、北九州学研都市版のCSA を提案するに至った。
次に、コミュニティのマネジメント体制の構築を目的として、コミュニティの形成に始まり、住民が主体となり活動もコミュニティそのものも持続可能なものとなるような仕組みの提案を行った。住民の意向に沿ったものにしなければならないため、住民の意見を広く聞き、多くのアイデアを活かし、活動が継続するように、利害関係者間でのより良い支援体制の構築を目指す。そこでこれまで作成した指標を原案とし、住民アンケート調査を実施し、この結果をうけてマネジメントの活動体制などの提案を行った。そして直接集まって議論するためのワークショップを実施し、更なる意見の集約を図った。
|
 |
研究の流れ
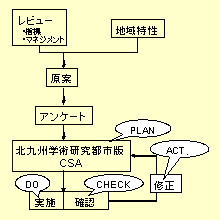
|
 |
|
1.その項目に対して、日頃どのような問題を感じているか
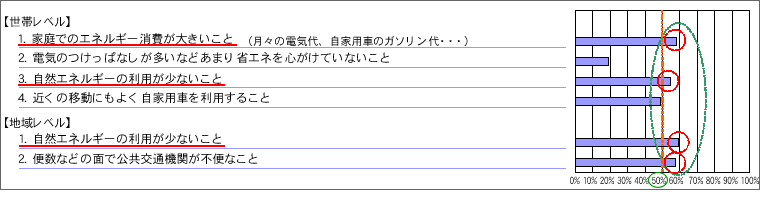
|
2.今後どのようになることが望ましいか
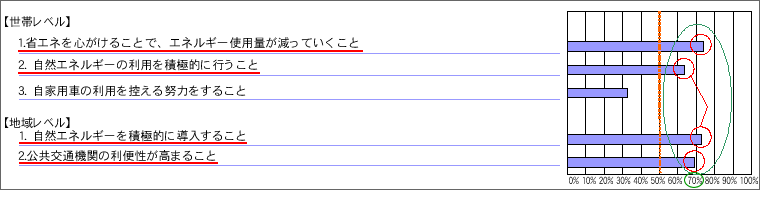
|
3.それを実現するためには、どのような行動と条件が必要か
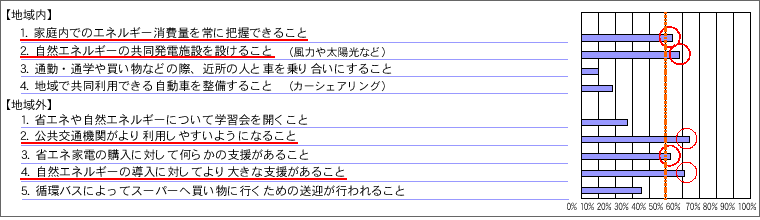
|
|
図 :アンケート結果 エネルギー
|
 |
CSAにおける役割分担案
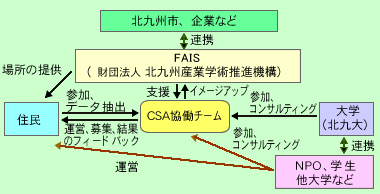
|
 |
指標項目案
| 環境 |
1.ごみ |
| 2.エネルギー |
| 3.水資源 |
| 4.自然環境 |
| 快適性 |
5.音環境 |
| 6.まちなみ |
| まちの活性度 |
7.住民交流 |
| 8.教育・文化 |
| 安心・安全 |
9.交通 |
| 10.治安 |
| 11.健康 |
|
|
|